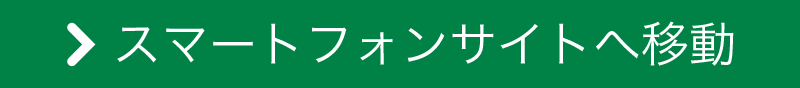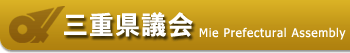三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 請願・陳情 > 令和7年定例会9月定例月会議 請願一覧 > 令和7年9月 請47
令和7年定例会9月定例月会議 請47
| 受理番号・件名 | 請47 防災対策の充実を求めることについて |
|---|---|
| 受理年月日 | 令和7年9月25日 |
| 提出された 定例会 |
令和7年定例会9月定例月会議 |
| 紹介議員 | 荊原 広樹、龍神 啓介、吉田 紋華、難波 聖子、芳野 正英、喜田 健児、中瀬 信之、山崎 博、山内 道明、村林 聡、長田 隆尚 |
| 付託委員会 | 教育警察常任委員会 |
| 請願要旨 |
(請願の趣旨) 子どもたちの安全・安心を確保するため、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実をはかるよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い申し上げる。 (請願の理由) 2025年3月31日、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの報告書が防災担当相に手渡された。想定される死者数は最悪の場合29万8000人、津波によるものが最も多くなると予想されている。防潮堤の建設や津波避難タワーの整備など、迅速な避難にむけたとりくみがすすんだにも関わらず、死者数が前回の予想32万人から8%ほどの減少にとどまっている。 2022年12月現在、三重県においては、公立小中学校の全体の25.1%にあたる124校の小中学校が、県の公表する津波浸水想定区域内に立地し、うち108校は避難所に指定されている。時間的に余裕をもって避難できる高台が周辺になく、津波に対する安全性が確保されない学校については、高台移転や高層化などの対策が求められている。ワーキンググループの報告では、対策がさらにすすめば犠牲者は大幅に減るとの指摘もあり、早急な対応が必要である。しかし、国による津波対策のための不適格改築事業については、補助要件である「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく「津波防災推進計画」の策定が全国的にもすすんでおらず、支援制度の活用がむずかしい状況である。補助要件の緩和、補助対象の拡大等支援制度のさらなる拡充を求める。 災害は、いつどこで発生するかわからない。避難所の運営に関しては、それぞれの自治体が施設やスペース、資材、人材を十分に確保するためにも、国からの財政的支援の充実が不可欠である。避難生活などで体調を崩して亡くなる「災害関連死」の防止をはじめ、性やプライバシーに関する課題への対応、外国人、介助・介護が必要な高齢者、障がい者、女性、乳幼児への配慮など、まだまだ改善すべき課題は山積している。国の責任において、安心して被災者が避難できるように備えるべきである。過去の災害に学ぶとともに、「三重県災害時学校支援チーム」の支援活動をつうじてえられた経験や知見をいかし、最善の備えを整えていくという考えのもと、防災に関わる施策がさらに充実されることを強く望むところである。 以上のような理由から、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実をすすめることを強く切望するものである。 |
ページID:000304096